お年玉の金額相場を年齢別に紹介!いつからいつまで渡すべきか・注意すべきマナーも解説
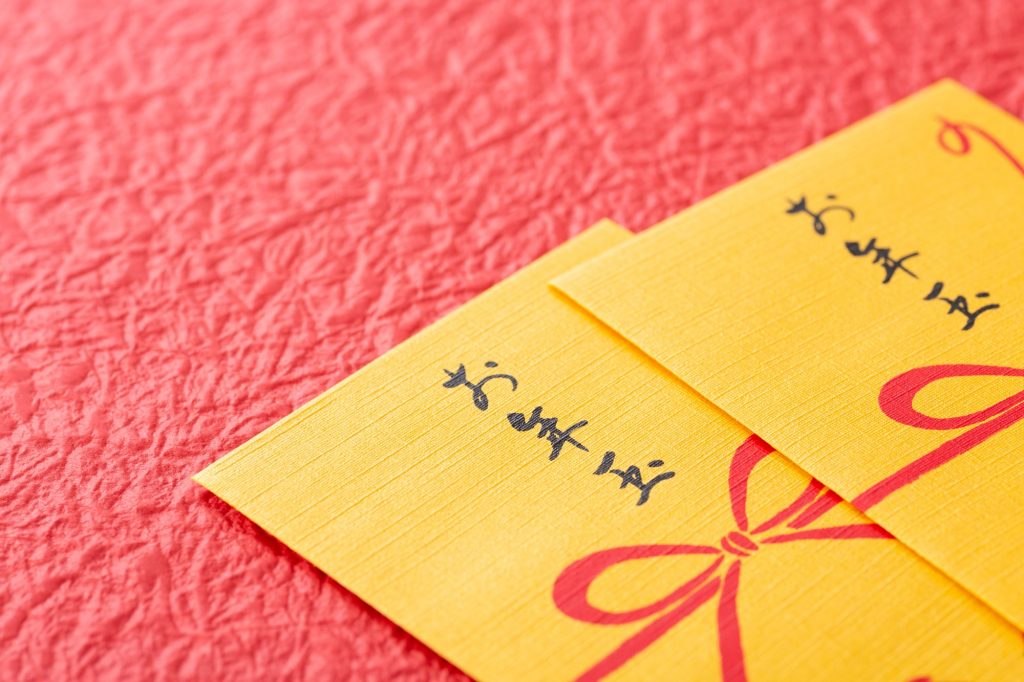
子どもの頃、お正月になるとお年玉をいくら貰えるのか楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。お年玉を貰った経験があっても、大人になって渡す立場になると、相場はいくらなのかと悩む方もいるでしょう。
実はお年玉にもマナーがあり、渡すときに注意すべき点がいくつかあります。
そこで今回の記事では、お年玉の相場やマナーなどについて解説します。お年玉の相場を年齢別に紹介するので、親戚や友達・近所の子どもたちに渡すときの参考にしてみてください。
※記事の内容は記事公開時点のものです。
お年玉の由来

お年玉の由来はいくつか説がありますが、最も有力とされているのは「御歳魂」です。年末年始に歳徳神(通称:歳神)さまにお供えした丸餅を、家長から家族や奉公人にわけ与えると、その一年は健康と豊作に恵まれると考えられていました。
丸餅が玉のような形をしていることや、歳神さまの魂(としだま)が込められていることが、お年玉の語源と考えられています。
元々は丸餅をお供えしていましたが、お餅をついて歳神さまへお供えする家庭が徐々に減っていき、昭和30年代から手軽に用意できるお金に変わっていったと考えられています。また、昔は大人同士で渡すこともありましたが、現在では大人から子どもに渡すものになっています。
【年齢別】お年玉の金額相場

お年玉の金額は、核家族が増えて渡す人数が減ったことから相場が上がったといわれています。
実際にどのくらいの金額を目安にしてお年玉を渡したらいいのか、年齢ごとに紹介します。お年玉を渡すときの参考にしてみてください。
乳幼児(0〜2歳)
0~2歳の乳幼児の場合、まだ物心がついておらず、お金の価値もわからないことからお年玉をあげないというケースが多いです。
特に、近所に住んでいる子どもや友達の子どもには、渡さないのが一般的です。親類の子どもに渡すときには、500~1,000円が相場です。お年玉を渡すのは、お金の価値が理解できるようになってからでも問題ないでしょう。
未就学児(3〜6歳)
小学校へ入る前の未就学児であれば、500~1,000円程度が相場です。
お年玉をプレゼントする側の年齢が高いと3,000円といったケースもありますが、基本的には子どもがお菓子を購入できるくらいの金額を渡すのが一般的でしょう。
また、お年玉を渡すときは子どもに直接でもよいですが、遊んでいるうちになくしてしまう可能性もあるので、親が見ている前で渡すようにしましょう。
小学校低学年(1〜3年生)
小学校へ入ったばかりの低学年の子どもには、1,000~3,000円を渡す方が多いです。
最低でも1,000円を基本として、学年に応じて少しずつ金額を上げていく傾向があります。
ただ、親戚の子どもの場合はお年玉をプレゼントする人数によって金額を調整し、子どもの間で格差が出ないように工夫するケースもあるので、一律にするのではなく柔軟に金額を変えることをおすすめします。
小学校高学年(4〜6年生)
小学校高学年になると、3,000~5,000円が相場ですが、3,000円を渡す人が多いようです。
少しずつ自分の財布からお金を払うことが増えてくる時期なので、お金の価値を理解したり正しい金銭感覚を身につけたりするためにも、大人が配慮することが大切です。
もしかしたら、自分が子どもの頃は5,000円以上貰っていたことがあるという方もいるかもしれません。祖父母は多めにお年玉を渡す傾向があり、相場と少しかけ離れているので注意しましょう。
中学生
中学生に渡すお年玉は、5,000円前後が相場です。
5,000円前後といっても、「4」がつく金額を渡すのはマナー違反なので4,000円は避け、少なくとも3000円を渡すことをおすすめします。
一般的な相場は5,000円ですが、もし自分の子どもが同年代ならば、相場にかかわらず貰った金額と同額をお年玉として渡しましょう。
高校生
高校生になると、水準が上がりお年玉の相場は5,000~10,000円です。
基本的には5,000円を最低金額として、中学生までどのくらいの金額を渡していたかによって5,000円もしくは10,000円を渡す傾向があります。
ここまで年齢別の相場を紹介してきましたが、地域によっては年齢と関係なく一律というところもあります。たとえば沖縄は年齢に関係なく1,000円という習慣があるので、それぞれ地域のならわしを参考にしながら金額を決めましょう。
大学生
大学に入学すると、もうお年玉は出さないという方が多いです。
もしお年玉を渡す場合は、10,000円程度が相場になります。金額も大きくなるので、ご自身の経済状況や相手との関係を考慮しましょう。お年玉をあげなかったとしても特に失礼にはならないでしょう。
お年玉を渡す年齢はいつからいつまで?

お年玉をいつからいつまで渡せばよいのかと悩む方もいるかと思いますが、明確には決まっていません。
一般的には、幼稚園や保育園へ入園してから高校を卒業するまでのようです。
それ以外にもお年玉を渡しはじめる、もしくは渡すのを止めるタイミングの目安があります。以下のようなものなので、迷ったときには参考にしてみてください。
お年玉を渡しはじめるタイミング
- ・0歳(産まれた年)
- ・幼稚園・保育園へ入園した年
- ・小学校に入学した年
お年玉を渡すのをやめるタイミング
- ・高校を卒業した翌年
- ・社会人になった年
- ・成人した歳
これらはあくまでも目安なので、相手との関係や自分の経済状況も考慮しながら検討してみてください。
お年玉を渡すときにおける5つのマナー

お年玉を渡すときにもマナーがあります。
この章では、お年玉を渡すときに注意すべきことを解説します。守れているか、チェックしてみてください。
お札の表裏・折り方
お札には裏と表があり、肖像が描かれている方が表です。お年玉としてポチ袋にお札を入れるときには、当然折らないと入りません。
ポチ袋には、お札を開いた際に表が見えるように折って入れましょう。
表が内側にくるように左から右へ順に三つ折りにすると、お札を開いたときに表が見えます。ポチ袋の大きさによってはお札を4つ折りにしないと入らないケースもありますが、「4」という数字は縁起が悪いのでなるべく避けた方がよいでしょう。
硬貨の入れ方
お札と同じように、硬貨にも表と裏があります。絵柄や漢数字が書いてあるのが表、製造年月が書かれてある方が裏です。
お年玉として硬貨を渡すときには、取り出したときに表が見えるようにポチ袋に入れるのがマナーです。
お年玉に硬貨を入れるのは、年齢の低い子どもへプレゼントするケースがほとんどですが、そのときにも最低限のマナーとして硬貨の裏表に注意しましょう。
お金はポチ袋に入れる
お年玉を渡すときは、そのままお金を渡すのではなくポチ袋に入れるのがマナーです。
ポチ袋の表には相手の名前を、裏には自分の名前を書いて渡しましょう。
急にお年玉を渡すことになっても困らないよう、年末年始はポチ袋を常備することをおすすめします。万が一のことを考えて、外出する際にもバッグへ入れておきましょう。
コンビニやスーパーなどでもポチ袋を売っています。それ以外にもいろいろな種類のポチ袋が販売されているので、ぜひ下記をご覧ください。
縁起の悪い数字を避けた金額にする
「4」や「9」の数字は忌み数といわれ縁起が悪いので、避けるのがマナーです。「4」は「死」を、「9」は「苦」を想像させる数字です。そのため、
4,000円や9,000円など「4」と「9」がつく金額はよほどの事情がない限り避けましょう。
相手が喪中の場合は「お小遣い」として渡す
相手が喪中の場合は、お年玉ではなく「お小遣い」として渡しましょう。
相手だけではなく、自分自身が喪中の場合も同様です。
喪中であれば、本来はおせち料理やお正月の飾りなどお年賀に関することは控えるのが一般的です。しかし、お年玉を楽しみにしている子も多いので、お年玉を渡したい場合は「お小遣い」と書いて渡しましょう。
また、喪中の相手に「おめでとう」という言葉はいわないのもマナーのひとつなので、お小遣いを渡すときに注意しましょう。
金額相場やマナーを理解してお年玉を渡そう!
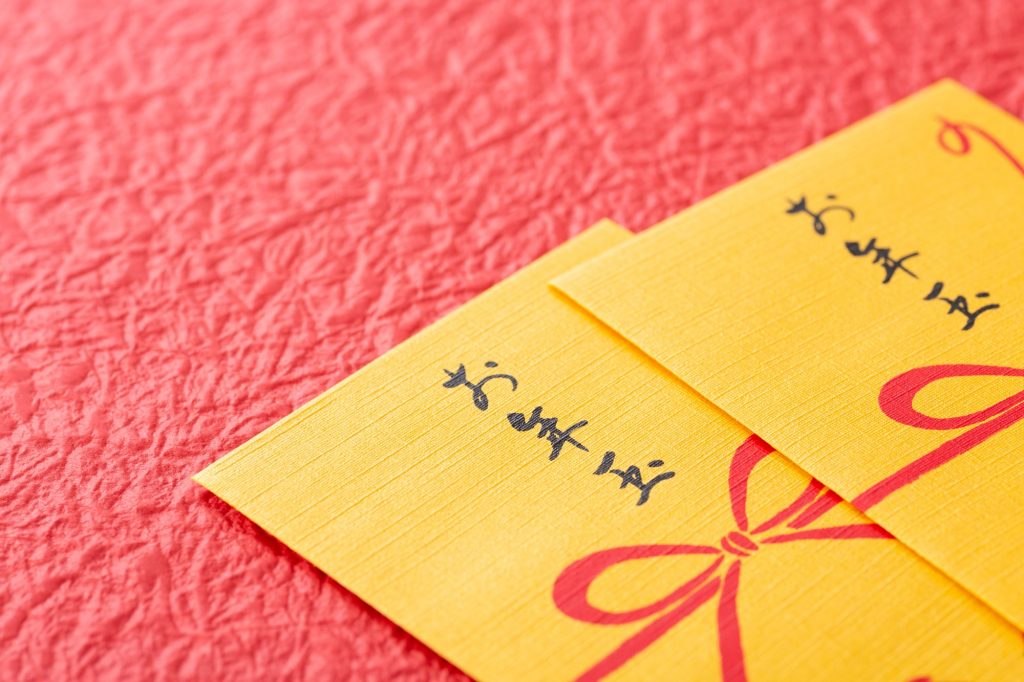
お年玉は、年末年始に歳徳神さまにお供えした丸餅を、家族や奉公人にわけ与えたことが由来だといわれています。やがて丸餅からお金を渡すようになり、昔は大人同士でやり取りすることもありましたが、現在は子どもに渡すように変化しました。
一般的には、物心がつく幼稚園・保育園へ入園する頃から、高校を卒業するまでが、お年玉の対象です。また、お年玉の相場はあるものの、相手との関係や自分の子どもが貰った金額、地域の習慣などを考慮して金額を検討しましょう。
お年玉を渡すときには注意すべきマナーがいくつかあります。
お札や硬貨は表が見えるように入れる、ポチ袋に入れるなど、しっかりとマナーを理解したうえでお年玉を渡すようにしましょう。
この記事が役に立ったら☆をタップ
役に立った





